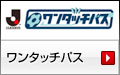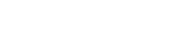新田常務取締役が埼玉大学で講義
[クラブ]本日2日(月)、新田博利常務取締役が埼玉大学の公開講座「スポーツ・マネジメント概論」にて、「これからの浦和レッズ・『世界基準』と『地域密着』」をテーマに講義を行ないました。
今年で4回目となる「スポーツ・マネジメント概論」は、浦和レッズと協定を締結している埼玉大学にて毎年公開講座として開講されているもので、レッズからの講師は5月12日に授業を行なった藤口光紀代表に続き、2人目となります。
5月28日に新田常務取締役がシドニーへ招かれて英語で行なった講演の話をきっかけに、「浦和レッズのポジション」では現在のレッズ、Jリーグが世界の中で置かれた状況について、「これからのレッズ」ではレッズの中期ビジョンについて、「クラブ運営構造改革」ではレッズが世界基準を目指すうえで、クラブをどう改革していくのかといったセンテンスごとに説明を行ないました。
そして、昨年のACLの挑戦に際して、特にアウェイでどういう準備を行なったか、その中でハートフルクラブが果たした役割について振り返りました。
また、グローバル(世界)とローカル(地域)を合わせた造語である「グローカル」について、「浦和発アジア経由世界行き」という基本的な目標に対して、クラブとしてどうやって取り組んでいくのか、石油枯渇後に観光とスポーツ立国を目指すUAEの事例を挙げて説明しました。
浦和レッズからはこの後、7月7日(月)に落合 弘ハートフルクラブキャプテンが講師を行ないます。
新田博利常務取締役
「FIFA(国際サッカー連盟)には現在208の国と地域が加盟しています。一方国連の加盟国・地域は192ですから、実にFIFAの方が多くの国や地域が加盟しています。サッカーがインターナショナルなスポーツであることの証明です。世界中どんなところでもボール1個でコミュニケーションを取ることができます。それがサッカーの魅力です。
私自身もプレーヤーとして、サッカーから多くのことを学びました。そして、社会人になった後も、サッカーの経験が社会にも生きていることに気付きました。今、浦和レッズというチームには、できることがいろいろあるのではないかと思っています。
先日のシドニーのカンファレンスの時に、FIFAの方が話した1つのキーワードが非常に印象に残っています。『これからはチャリティーからレスポンシビリティだ』ということです。チャリティーは『モノをあげる』ことですが、レスポンシビリティというのは『責任を果たす』ということです。私も、浦和レッズというクラブのスタッフの一人として、サッカーを通じて、人々の『笑顔』を作っていけるのか、などの責任を果たしていきたいと思っています」